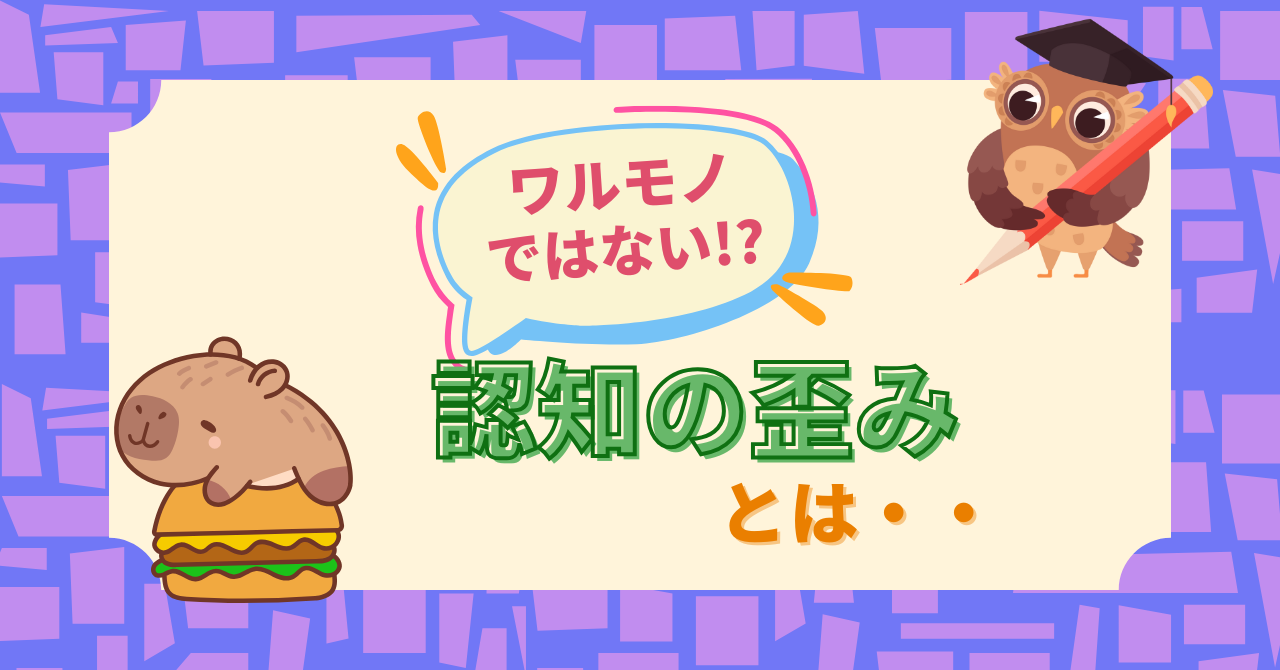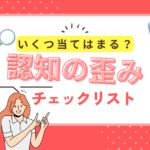先生、“認知の歪み”って聞くと、なんだか怖い言葉に思えます。僕の考え方は間違ってるってことなんでしょうか?

カピバラのカピオは少し不安そうに尋ねました。
セージ先生はやさしく笑って答えます。

いいや、カピオ。実はみんな多少の“歪み”を持っているんだ。だから大丈夫なんだよ
1.認知の歪みとは?
自動思考の中でも、自分を苦しめる極端な考えを「認知の歪み」「認知の偏り」などと呼びことがあります。
「歪み」や「偏り」と聞くと「悪いものだから取り除かなきゃ」と思うかもしれませんが、実際は誰にでも自然とあるものです。
しかし例えば――
- 「失敗したら全部ダメになる」
- 「あの人が返事をくれないのは、自分を嫌っているからだ」
こうした極端な考え方は、感情を揺さぶり、ストレスや不安を強めてしまうことがあります。
2.認知の歪みも“悪者”ではない

大事なのは“歪みを追い出すこと”じゃないんだ。考え方には必ず理由があるからね
たとえば青信号を渡るときに、自動的に「青なら渡れる」という考えが思い浮かぶ例を以前にも挙げました。
でも、もし社会のルールが変わって「赤で渡る」になったとしても、しばらくは赤で止まってしまうはずです。
これは「過去のルールに従った考え方」が残っている状態です。
認知の歪みも「昔は役立っていたけれど、今はあまり役立っていない考え方」と言えます。
3.手放し方のコツは“やんわりと”
「歪んでるから消さなきゃ!」と思うと、かえって苦しくなります。
代わりに、こう考えてみましょう。
- 「今までありがとう。でも今はあまり役立ってないかも」
- 「必要なときはまた使うかもしれないけど、今は少し置いておこう」
追い出すのではなく、お礼を言って手放すイメージです。
そうすることで、心が軽くなりやすくなります。
認知の歪みについては、いくつかパターンがあると言われています。
詳しくは以下の記事にも記載がありますので、ご興味があればご覧になってください。
歪んでるって聞いて焦ったけど…実はみんなそうなんだって分かってホッとしました!

次回はいよいよ、カピオが「自動思考」を整理していくために使う “コラム表”というワークシート を紹介します。